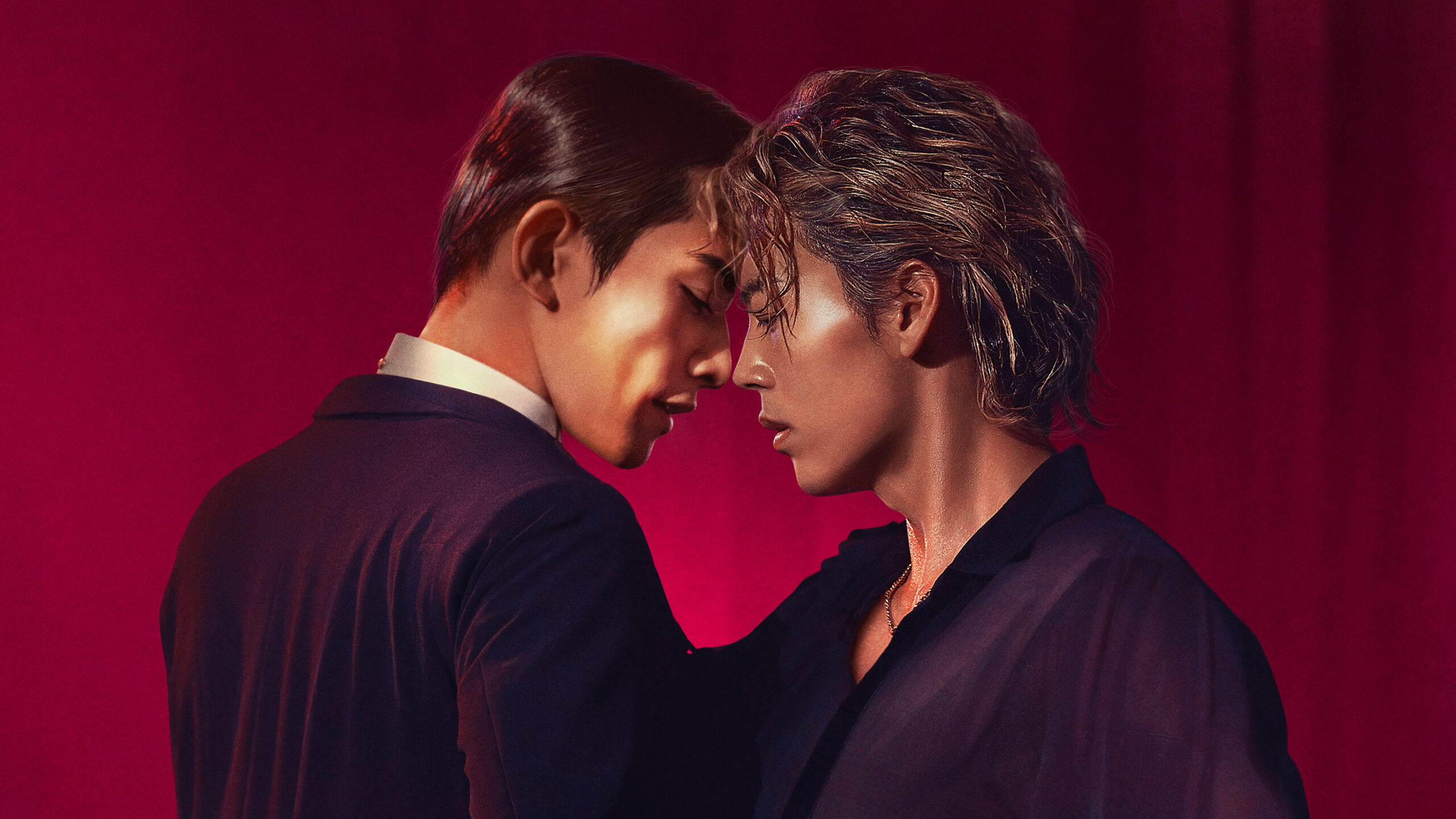『週刊文春』、勝谷誠彦、町山智浩、ひろゆき……etc 珠玉の交遊録『博士と僕と平成サブカル史』 文藝春秋・編集者、目崎敬三さんインタビュー

文藝春秋の編集者として、浅草キッド『お笑い 男の星座』をはじめ数々の話題書を手掛けてきた目崎敬三さん。今年3月末に文藝春秋を定年退職するものの、翌月にはお笑い芸人の水道橋博士さんが放送作家の若林凌駕さんと共に立ち上げた「虎人舎」という出版チームから、冊子『博士と僕と平成サブカル史』を発行。
目崎さんが文藝春秋で働いていた時代の中から平成元年から31年までの期間を1年ごとに振り返った内容で、各ジャンルの著名人たちとの知られざる交流、エピソードが赤裸々に記されている。フリーペーパー「YABO」vol.20に引き続き、目崎さんに編集者時代を振り返っていただいた。
●まさかの文藝春秋入社
——『博士と僕と平成サブカル史』は文藝春秋での思い出を綴った冊子ですが、目崎さんがそもそも文藝春秋に入社された経緯から教えてください。
目崎 学生時代からメディアで働いてみたいという気持ちがあったんですよ。僕は高校時代アニメにどっぷりとハマって、慶応義塾大学に入学してからはアニメーション研究会に所属してね。大学2年生の時に『機動戦士Zガンダム』(85年)が始まったんだけど、3、4歳上のアニメ研究会のOBたちがその現場で働いていたんです。なおのこと自分の感性でものを作り出したい気持ちが昂ってきて、漫画好きということもあって、出版業界に入ればいいなと。
当時、大手の新聞は800万部が当たり前で、読売新聞はいたっては1000万部発行していたんです。当時ソ連の機関紙プラウダが1000万部だったことから、「読売新聞は日本のプラウダ」と言われていたぐらいで。
——本当に出版業界に勢いがあって、華やかだった時代ですね。
目崎 それでいろいろと出版社を受けてみたところ、偶然にも文藝春秋に受かったんです。これは自分でも意外でした。客観的に自分を見て、漫画でもマイナーな作品が好みだったので、1000万人に届ける現場より、10万人規模に向けたメディアが最適だろうと思っていましたから。当時、月刊誌『文藝春秋』が80万部発行で国民雑誌と言われていて、『週刊文春』にしても50万部で出版業界の大メジャーでしたしね。
——『博士と僕と平成サブカル史』で、若き日の目崎さんが文藝春秋の社内の空気に馴染もうと苦闘する姿が赤裸々に描かれていますね。
目崎 冒頭でも書いているように、編集部に電話を掛けてきた松本清張さんに対して、「どちらの松本さんですか?」と粗相したりしてね(笑)。研修期間を経て『週刊文春』編集部に配属されたけど、自分に合わないと最初は苦悩しました。
だけど、当時『文春』の編集長は花田紀凱さんという、現在『月刊Hanada』を手がけている方だったんですが、理解を示してくれて。「目崎はオタクだから」と、泉麻人さんや宅八郎さんといったサブカルの人たちとの仕事をあてがってくれたんです。僕はそういった人たちに揉まれながら、だんだん自分のキャラクターが確立して仕事をこなせるようになりました。
●入社2年目でビートたけし担当に
——仕事に慣れたとは言え、『週刊文春』編集部は大変だったと思います。
目崎 確かに『週刊文春』時代は、休日は合併号が出る正月、ゴールデンウィーク、お盆の年3回だけで、あとは朝から晩までひたすら仕事してました。でも、楽しかったです。僕は事件記者みたいなことは1回もやってないんだけど、サブカルや文化好きということから、入社2年目でいきなりビートたけしさんのコラムを任されたんですよ。
——すごいですね!
目崎 毎週たけしさんに会うのがすごく楽しみで、「歌舞伎を観に行こう」とか「最近、こういった映画を観た」といろいろと話してくれました。あの時代のたけしさんは、僕にとって親戚の面白いおじさんという感じなんですよ。
——たけしさんと言えば、怖いイメージもありますが。
目崎 周りのスタッフさんたちがピリつくことはあったけど、こちらを萎縮させるようなことは全くなかったです。長嶋茂雄さんもそうですが、カリスマと呼ばれる人たちって、近くにいる人に安心感を与えてくれる。僕はたけしさんに会うたびに心が落ち着いたのを覚えています。
当時のたけしさんは『オレたちひょうきん族』や『オールナイトニッポン』の放送が終わったあたりで、比較的のんびりできた時期だったのもあるんでしょうけど。そうやって『週刊文春』時代は、文化の純度を高めさせていただきました。
●勝谷誠彦、柳澤健との思い出
——『文春』時代、後にジャーナリストとして活躍される勝谷誠彦さんが先輩として編集部に所属されていたとのことですが。
目崎 勝谷さんのことは『博士と僕と平成サブカル史』にもいろいろと思い出を書かせていただいたけど、特に印象に残っているのは、平成元年に起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件ですね。
『文春』はこの事件を報道する際に、今では考えられないことだけど、「野獣に人権はない」と実行犯の男子高校生4人の実名を晒したんです。編集長の判断もあっただろうけど、勝谷さんは現場で取材していて、「こんなにも酷い奴らがいるのか」と非常に憤りを覚えた。それぐらい陰惨な事件だった。
未成年を実名報道したことで様々な議論を呼んだし、「そこまでして雑誌を売りたいのか」と批判も受けましたが、勝谷さんの根底に義憤があったのは確かです。
——勝谷さんは関西出身ということもあって、関西のお茶の間では歯に衣着せぬコメンテーターとしてお馴染みでした。
目崎 その頃から勝谷さんはテレビのワイドショーにもコメンテーターとして出演するようになって、編集長の花田さんも「『週刊文春』の宣伝になるんだったら、どんどんテレビに出ていいぞ」と背中を押していましたね。
——そういった意味では、『文春』編集部は風通しが良かったんですね。
目崎 だって、勝谷さんの1つ上の先輩だった柳澤健さんは仕事しながら編集部でギターを弾いてたんだよ(笑)。
——柳澤さんは、『1976年のアントニオ猪木』をはじめ、プロレス系のノンフィクションで著名な方ですが、元々は『文春』の編集者だったんですね。
目崎 柳澤さんは現在スポーツライターとして活躍されているけど、『文春』時代はグラビアページ担当で、とにかく面白いことをするのが好きなんですよ。仕事以外にもいろいろと楽しみを見つけるタイプというか。
当時は土日も出勤しないといけないのに、「土曜日の午前中は草野球をしたいから」と言い出したことがあって(笑)。編集長も「だったら、しょうがない」と容認していました。柳澤さんは2005年ぐらいに文藝春秋を辞めたけど、今でも仲良くて、一緒に女子プロレスを観に行ったりしています。
——女子プロレスと言えば、目崎さんはX(旧Twitter)のプロフィールに、女子プロレスラーの広田さくらファンクラブ副会長と記載していますが。
目崎 これも柳澤さんがキッカケです。柳澤さんは広田さくらさんのことが大好きで、2010年に「彼女はもっとブレイクするべき存在だ」と、彼女のファンクラブまで立ち上げたんです。それで「俺が会長で、お前は副会長だから」と指名されてね。さらにファンクラブ限定で広田さくらさんのグラビアやインタビューを掲載したミニコミを作ることになって、「お前が編集をやれ」と。
——押し付けられるような感じだったんですか。
目崎 そう見えるけど、これには裏があって、2010年当時、僕は出版部から宣伝プロモーション部に転属になったんです。柳澤さんはそのあたりの機微をちゃんと見ていて、「お前は宣伝よりも、編集の仕事がしたいだろう」と気持ちを汲んでくれての指示だった。有り難かったですね。柳澤さんって人情家でもあるんですよ。
●芥川賞&直木賞授賞式のライブ配信
——『博士と僕と平成サブカル史』を読むと、2011年にニコニコ動画で芥川賞と直木賞の授賞式のライブ配信が行われた際、目崎さんが裏方として携わっていたという記述があって、とても驚きました。
目崎 そうそう。『平成サブカル史』にも書いたけど、その前に2ちゃんねるの掲示板「独身男性板」で盛り上がっていた『電車男』の書籍化を考えて、2ちゃんねるの開設者であるひろゆきくんにも話をつけていたんだけど、結局企画が通らなくて、ライバルの新潮社に出し抜かれてしまった。けれど、そのあたりから出版社がウェブに近づく流れが出来つつあったんだよね。
——ニコニコ動画での授賞式のライブ配信が行われたのも、その流れがあったからですね。
目崎 ひろゆきくんはすでに2ちゃんねるを卒業して、ニコニコ動画を運営しているドワンゴに携わっていました。僕もその関係からドワンゴの方たちと親しくなっていったんです。その中に早川書房から転職したタカハシさんという方がいて、「自分は出版社出身なので、出版社のコンテンツをやりたい。例えば文藝春秋が取り仕切っている芥川賞と直木賞の受賞式を中継したいんです」と提案してきて、それで出版局長の庄野音比古さんに話を持っていったところ、「俺もそういうことをやりたいと思っていたんだよ」と、とんとん拍子で決まっていきました。
『平成サブカル史』では、庄野さんが最初に発案したように書いてあるけど、実はすでにドワンゴのタカハシさんからも話は来てたんですよ。
——実際に動画の反響は想像以上だったとのことですが。
目崎 ちょうどその年に芥川賞を受賞したひとりが『苦役列車』の西村賢太さんで、授賞式のスピーチで「風俗に行こうかなと思っていました」と放談して(笑)。過激な内容にネット民が湧き上がって、視聴者数もすごかった。
——現在のSNSなどでの芥川賞、直木賞の文化的な盛り上がりは、そのインパクトと流れがあったからだと思います。
目崎 いずれにしても、あの授賞式のライブ配信は、ひろゆきくんがキーパーソンとして関係していて、やっぱりそこは大きな要素ですよ。でも、『電車男』の件があったから、ひろゆきくんとは会うたびに、「相変わらず目崎さんは仕事していないんでしょう」とイジられるんだけどね(笑)。
●文藝春秋という磁場と町山智浩
——『博士と僕と平成サブカル史』を読んで、目崎さんから感じるのはいろんな人を引き寄せる磁場なんです。文藝春秋自体がそういう磁場を持っていたと思うのですが。
目崎 ひとつあるのは、文藝春秋は僕が入社した時点で65年もの歴史があって、今の感覚で言うとポータル、昔で言えばサロンのような、作家さんや新聞記者といった人たちが意見を出し合う環境がすでに出来上がっていたんです。
それこそ『月刊文藝春秋』には政治家や著名な経済人に関するお堅い企画を掲載していますよね。だけど、僕はそういうところには上がらないけど、とにかく強烈な個性を放つサブカルチャーの方に魅力を感じるんです。
——それこそ目崎さんは、お笑い芸人の水道橋博士さんや映画評論家の町山智浩さんなどの書籍を手掛けていますね。
目崎 博士も町山さんも表現者として出力の高い人たちですけど、文藝春秋という磁場を使えば、さらに5倍、10倍の出力でアンプリファー(増幅)できるんじゃないかなという思いがあって。実際にお2人の書籍はヒットしたしね。
——特に2008年に発行された町山さんの『アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない』は、現在『週刊文春』やラジオ番組などの媒体でアメリカの最新情報をお伝えする町山さんのスタンスを決定付けた一冊だと思います。
目崎 あの本は僕が初めて手がけた町山さんの書籍なんだけど、そもそもは別の週刊誌に連載していたコラムをまとめたものなんです。その雑誌の版元は書籍化する予定がなかったらしく、町山さんから直々に「文藝春秋で書籍化してほしい」と企画をいただいて。ちょうどオバマ大統領が就任する直前で、日本でもオバマブームが起きて、「なぜアメリカ人は彼を大統領に選んだのか」と多くの人がアメリカの実情について興味を持った。そういう意味でタイミングが良かった。
——それから『週刊文春』で町山さんのコラム「言霊USA」の連載が始まって、ある程度連載の原稿が溜まったら書籍化するという流れが出来ましたね。
目崎 町山さんは若い頃から宝島社の名編集者として有名で、憧れの存在でした。1995年に洋泉社で雑誌『映画秘宝』を立ち上げて。1997年にアメリカに移住することになった際に、お別れ会にお邪魔してご挨拶させていただきました。
「いつか一緒に仕事が出来ればいいな」と思ったんだけど、そこから『アメリカ人の半分は~』まで約10年かかったんですね。僕が文藝春秋で最後に手がけた町山さんの書籍が『独裁者トランプへの道』で、アメリカもかなり様変わりしちゃったけど(笑)。
●書籍になるまでに10年、文庫化に10年の仕事
——目崎さんが編集者として、今までで最も達成感を感じた仕事を教えていただけますでしょうか。
目崎 う~ん。いろいろ思い出深いものばかりだけど、達成感と言えば、2010年に発売した本橋信宏さんの書籍『新・AV時代 悩ましき人々の群れ』になりますかね。本橋さんはフリーライターなんだけど、AV監督の村西とおるさんと関係が深い方だったんですよ。この本もタイトルが示すように村西さんを中心にAV業界の知られざる実態に迫ったノンフィクションです。本橋さんとの繋がりは『週刊文春』の書評を依頼したのがキッカケなんだけど、それからこの本を作るのに13年もの月日がかかりました。
この本を作ったあと、僕は出版部から離れることになるんだけど、その間にNetflixで村西とおるさんを題材にした『全裸監督』(2019年)が大ヒットして、その影響で新たに『新・AV時代 全裸監督後の世界』(2021年)というタイトルで文庫を出すことになって。単行本が出来上がるまでに約10年、さらに文庫化に約10年と、時の流れを感じさせる意味でも自分の中で感慨深い仕事です。
——目崎さんは今年2025年3月末に文藝春秋を定年退職されて、これからフリーとして活躍されるとのことですが、今後の野望を教えてください。
目崎 新しい名刺に「編集・ライター」という肩書を付けたんですよ。まあ、順番はどっちでもいいんだけど、ライターを後にした方が収まりがいいかなって。会社を退職する際に、今までお世話になった関係者に「フリーの編集・ライターとしての活動していく所存でございます」と連絡して、いろいろと企画を出しているところです。やっぱり自分はメジャーよりもサブカルの世界の方が好きだから、自分の好きなことだけを今後もコツコツとやっていきたいですね。

<プロフィール>
目崎敬三(めざき・けいぞう)
1965年愛媛県生まれ。1988年慶應義塾大学卒業後、文藝春秋に入社。『週刊文春』『Number』編集部に所属し、2000年に出版部に配属。その後、宣伝プロモーション部、WEB事業部を経て、2021年に出版部に復帰する。2025年、60歳を迎え定年退職し、フリーの編集・ライターとして活動開始。
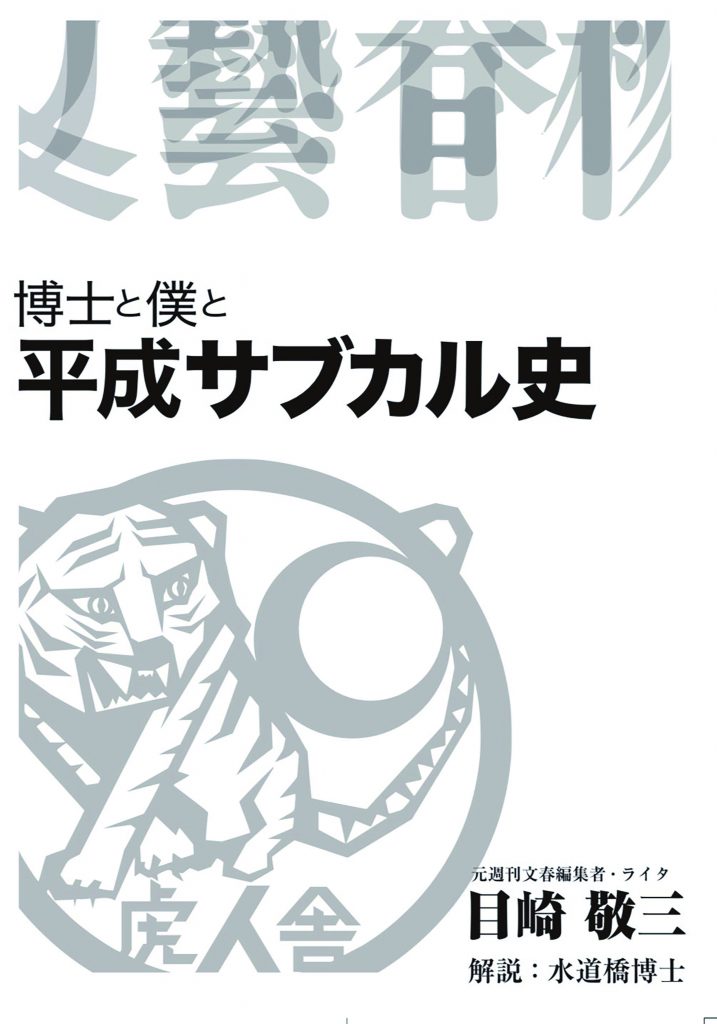
『博士と僕と平成サブカル史』
目崎敬三 著/1,000円(税込)/虎人舎 刊
※オンライン販売も開始!
目崎敬三さんと水道橋博士さんのダブルサイン入り!!
https://booth.pm/ja/items/6971214